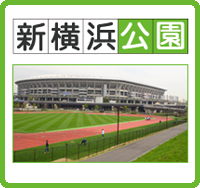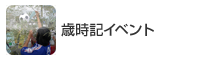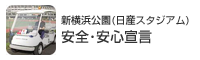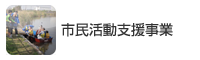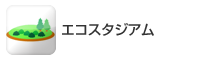?冬芝から夏芝への切替作業?
| みなさん、こんにちは! 早いものでJリーグ1stも中盤に差し掛かってきました。横浜F・マリノスは優勝を目指して見事に上位をキープしています。今が正念場というところでしょうが、ぜひともがんばっていただきたいものです。 さて、この時期その戦いの舞台となる芝も、マリノスの選手と同じように一つの正念場を迎えています。芝生は寒く厳しい冬を乗越え成育の時期を迎え、いよいよ冬芝から夏芝への本格的な切り替えシーズンが始まろうとしています。 そこで今回は、知る人ぞ知る『芝生の切替え作業』についてお話しましょう。 競技場に来場された方から、「ここは2種類の芝生を使っているんですよね。いつごろ夏芝の種子を蒔くんですか?」とか、「いつごろ張替えを行うのですか?」などと聞かれることがあります。横浜国際総合競技場は確かに2種類の芝生(夏芝と冬芝)を併用しています。しかし、冬芝から夏芝への切替えのために、種子を蒔いたり、張替えを行ったりはしていません。では、どうやって切替えをしているのでしょうか。 競技場では2種類の芝生を使用していますが(詳しくは「芝生のとっておきの話(1)」をお読みください。)厳密に言えば、夏型の芝生をベースとして使用しており、休眠してしまう冬場だけ冬芝の種子を蒔いて補っている。といった方が正しい表現だと思います。 冬芝は種子繁殖するので毎年秋口に種を蒔きますが、夏芝は樹木などと同じように春先になって気温が高くなってくると新しい葉を出して繰り返し育つ芝生なので、種まき等は必要がないのです。 そこで私たちがすることは、芽が出てきた夏芝が冬芝に負けずに少しでもはやく生え揃うようにしてあげることなのです。
では、具体的にどのようなことをするかをお話しましょう。 まずはじめにすることは、夏芝が休眠する冬までに、翌年芽が出る体力を蓄えさせることです。これは前年の夏から秋に掛けて芝生が貯蔵養分を蓄えるために、水や肥料を十分に与えて丸々太った状態にさせてから寒い冬を迎えるためです。 次に行うことは、冬場の時期から利用に支障ない程度でそれ以上に冬芝を育て過ぎないように心掛け、肥料等も控え目にすることです。これは春先になって気温があがり芝生が目覚めて芽が出始めた時に、秋口に蒔いた冬芝が覆ってしまって夏芝の出てくるスペースを奪わないようにするためです。 そして春先になり夏芝の芽が確認できたら、冬芝を間引く作業(バーチカット)で夏芝が繁殖する場所を作ってあげます。
そのスペースを夏芝が覆うようになり始めたら、穴あけ作業(エアレーション)で冬芝を乾燥させ衰退を促します。
しかし、この期間もJリーグなどの利用が入っているため、一気に冬芝をなくしてしまうことはできません。夏芝の増えるスピードに合わせて冬芝の量を少しずつ減らしていかなければならない点が難しいのです。 もうひとつ大切な作業が刈込みです。通常冬芝のときは20ミリ前後の高さ(刈り高)でカットしていますが、この高さでは出てきた夏芝に光が当たらず、せっかく出てきても枯れてしまいます。それを防ぐためには出来るだけ低く刈る必要があります。選手たちに迷惑を掛けずに行える高さとして競技場では12ミリ?15ミリに設定しています。この時期の芝生は1日に1?2ミリ伸びてしまうため、この刈り高で週3回程度の刈込みを行っています。 横浜F・マリノスの試合の時は15ミリでもやや短いため、前日(前々日)に刈込みを行うだけとしています。(当日試合時は伸びて17?18ミリ)先日、サッカー関係者から「もう少し長くてもよいのでは?」というお話がありました。「伸ばすことはできますが、短くして少しでも早く夏芝が育つような環境作りをしてないと、夏場になって冬芝が衰退したときに芝生が無くなってしまい、ご迷惑を掛けることになるかもしれません。」と説明したところ、ご理解をいただきました。 これら一連の冬芝から夏芝への切替作業を総称して「トランジッション作業」といいます。ですからこの期間は、3月中下旬より始まり7月下旬位までの長丁場となります。
一見すると同じ芝生のようでも、誰にも気付かれずに冬芝を夏芝へ切替えているのです。こんなところに注意しながら違った形でJリーグを見てみるのも面白いのではないでしょうか。 次回は「コンサート時の芝生管理」についてお話します。 | ||||||||||||