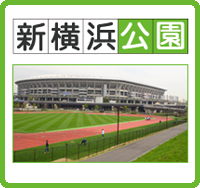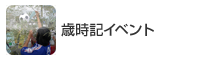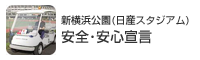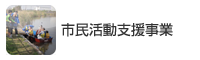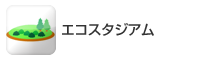★ 写真 オオタカの飛翔です。
撮影日時: 平成20年度3月28日午前11時30分頃
場 所: 新横浜公園北側園地
新横浜公園でオオタカの飛翔を見ることは珍しいことではありませんが、出会うとなんとなくうれしくなります。ゆったりとした羽の動きと、滑空する姿には王者の風格があります。オオタカが現れると、なぜかカラスが騒ぎ始め、蚊柱ならぬ「カラス柱」?が立ちオオタカを追ってゆきます。
中には、勇敢にもオオタカに襲いかかるものもおり、オオタカも幼鳥だと、カラスの迎撃に恐れをなすわけではないでしょうが、追い払われてしまうこともあります。猛禽とは言え数にはかなわない。多勢に無勢と言うところでしょうか。
春は恋の季節、オオタカとて例外ではありません。ただ、猛禽類の恋の季節は私たちが思うより早く、まだ、寒い2月ころから始まるようです。相手探しやら、新居の手配、オオタカもなかなか大変です。仲人さんは必要ないようですが春、忙しいのは人間だけではありません。新横浜公園に営巣の場所はありませんが、小机城址等の周辺緑地に複数箇所の巣を持ち、年によって使い分けているとのことです。
人間で言うと、高層ビルの屋上にあるペントハウスの住人と言ったところでしょうか。
チョッと、うらやましいですね。
★ 写真 スズメノカタビラ(イネ科)です。
撮影日時: 平成20年度4月2日
場 所: 小机フィールド外側の植栽地
枯れた芝生の中に緑の塊が転々とあり、日々芝生の緑が濃くなっていくように錯覚しますがこれは
芝生の芽吹きではありません。この草は「スズメノカタビラ」と言うイネ科の植物で古い時代に麦の伝播に伴い日本に帰化した畑地雑草と呼ばれる植物です。
畑地雑草ですが、新横浜公園では芝生雑草として勢力を広げています。この草の困ったところは踏みつけや低い刈り込みにも耐える特性を持っているため、芝生の中でも生育できることです。踏み付けや強い刈り込みにも耐える特性はスポーツターフにはもってこいの特性ですが芝生の生長を阻害するとのことで抜かれてしまいます。
それにしても不思議な名前です。「スズメ」は誰でも知っている鳥ですが、あまりほめられた名前とも思えません。「カタビラ」は単の着物のことで、巡礼者が羽織る袖のない衣のことを言います、鎖帷子は忍者の着るもの。経帷子(キョウカタビラ)と言えば死装束のことですから、これもあまりありがたい名前とは思えない。でも、スズメの名に付く植物はたくさんあり、同じ様な時期に育つのに「スズメノテッポウ」があります。これもイネ科の植物ですがこちらは畑ではなく水田に生えます。それにしても、帷子、鉄砲とは穏やかではありません。
★ 写真 カラスノエンドウ(マメ科)です。
撮影日時: 平成20年度4月3日
場 所: 新横浜公園北が側園地
カラスノエンドウ(マメ科エンドウ属)が花を咲かせ実をつけています。つる植物で赤い花なのですぐ分かります。支えとなるものがあれば何にでも絡み、あっという間に覆ってしまいます。成長の早い植物です。正式な和名は「ヤハズエンドウ」ですがカラスノエンドウの方が良く使われます。名前の由来は実の色にあり、熟すと鞘が黒くなるので「カラス」です。
マメ科ソラマメ属ですが、実の形やつるで伸びる姿を見ると「ソラマメ属」ではなく「エンドウ属」の方がふさわしいように思いますが、分類上はソラマメ属になります。そう言えば、ソラマメの鞘も熟すと黒くなるのでそんな点も共通しているのでしょうか。
カラスノエンドウも帰化植物で、原産地はオリエント、地中海地方とのことです。以前は食料用に改良されたこともあるそうですが、今は畑地雑草として生きています。昔は食べられたこともあり、今でも鞘や実を食べることは出来るそうですが、私は食べたことはありません。食べたことはありませんが、鞘を草笛として遊んだ記憶があります。
カラスノエンドウが勢いよく伸び始めるころには植物だけでなく昆虫の活動も活発になり、つるの先にアブラムシ(ゴキブリではありません念のため)の群生がみられ、それを食べる天敵のナナホシ、ナミテントウムシのかわいい姿を見ることが出来ます。もっとも、それを追い払う蟻の姿もですが。